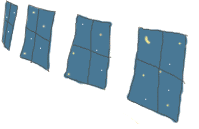|
 |
 |

広めの玄関ホール
 ようこそ ようこそ
誰かが、わが家を訪問した時に「私達はあなたを心から歓迎しています」
という
メッセージが伝わる家にしたいと私たち夫婦は考えていた。
考えてみれば、靴を脱いで上がってもらう来客は限られている。玄関での立ち話が多い。
私がちょっとした用事で誰かの家に行く。靴を脱いで上がるほどの用事ではない。
すると、このような応対が多い。その家の人は玄関を開けるが、開けたドアを手で押さえたまま話をするという光景だ。
その家の人は、家の中にいるでもなく、外に出るでもない。私も半ドアの前で
話し続ける。この不自然な格好で30分以上も話が続くこともある。押さえたままの腕が疲れているようだ。
来客を中に入れるでもなく、自分が外に出るでもないという微妙な位置は、日本人の対人関係の距離感を反映しているように思う。
しかし、私も妻もあれでは「歓迎しています」というメッセージを伝えられないと思った。
そこで、靴を脱がなくても家の中に入って、場合によっては座って話ができる空間がいいと思った。
そのためにはタタキを広くして、そこにベンチを置くという案になった。くつろげる玄関という発想だ。
また、妻は近隣の子どもに英語を教えている。クラスが始まる前に子どもが待っていたり、迎えのお母さんが
くつろげるような空間も欲しかった。
タタキとホールでユニットを一つ使うことにした。しかし吹き抜けでもないので、最近の大きな玄関と
比べれば決して大きくはないのかもしれない。
玄関ドアを開けると、奥行きが4.5メートル、幅が2.4メートルのホールになっている。
タタキの奥行きは1.7メートル。本当はタタキの部分を奥行き4.5メートルの半分以上取りたかった。
西山さんからは「タタキはどれだけの広さでも取れます」と聞いていた。しかし、途中で構造上無理という
ことが分かった。
「最大1.7メートルが限界です」と言われた時にはかなり落胆した。
でも西山さんに食って掛かっても仕方ないので、1.7メートルで諦めることにした。
ハイムで構造上できないことは、どんなに怒っても、懇願してもできない。
少し違うことをする場合には、初めの段階から設計での確認が必要だと感じた。
「これもユニット工法の功罪だな」と思った。
「でも、1.7メートルでもベンチを置くスペースは十分にある」と意識を変えた。
また、前のセッションで、Tさんのご主人がハイムの大工さんだということを記した。
Tさんのご主人に、家のプランを見てもらった時に、
「家の大きさと比較して、この玄関は広すぎますね。半分で十分」と言われてしまった。
だから逆に、わが家にはこれがちょうどいい大きさなんだと納得した。
 | 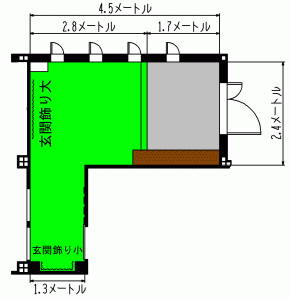 |
|
 【左図の説明】 【左図の説明】
右側が玄関ドア
図の灰色の部分がタタキ部分。
緑色の部分がフローリング。
茶色部分は2メートルの長さの下駄箱。
下駄箱はテーブル・タイプで上の空間は空いている。
正面の壁にはエコカラットで飾りを付けた。
この部分はインテリア手配。
また左に曲がった壁にもニッチの飾りを付けた。
|  |
 エコカラットの装飾 エコカラットの装飾
契約の第四週目(めまぐるしい六週間)にYさんの実邸を訪問したことを書いた。
玄関ホールのエコカラットの装飾が特に印象に残った。温もりと品があった。
その印象が強くて、わが家の玄関もエコカラットを貼りたいと考えた。
(エコカラットをご存知無い方は、名前で検索すれば直ぐにヒットします)
稲垣さんと相談して、イメージを伝える。そうすると稲垣さんが次回までに絵コンテを描いてくれる。
その絵を見ながら、検討を加えていく。
色やタイルの大きさ、横幅やテーブル部分の細工など…
そうやって最終的に出来たのが、下にある絵。
こんな絵を描いてもらった経験などないので、(正直なところ)とても気分が良い。
この装飾全体がインテリア手配になるので、それなりの出費になることは分かっているが
「多少の贅沢は、まあいいかぁ」という気になってくる。ケチって後悔するよりも
納得のいく家がいいなと思い始めている。
その気になったついでに、玄関ホールの奥の場所にも小さな装飾を付けることにした。ダブル装飾だ!
ああ…倹約家だったDavidは、どこに行ってしまったのか! お〜い、David 目を覚ませ!
だが、これらの装飾は予想よりも安かったのだ。
アイディアに対して見積を出してもらい、その金額を見て工事の可否を決めることができた。
 | 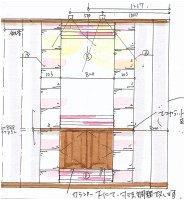 |
 稲垣さんが作ってくれた装飾のプラン。 稲垣さんが作ってくれた装飾のプラン。
 イメージをクリックすると拡大します。 イメージをクリックすると拡大します。
|  |
|
 |