 |
 |
 |

積水化学工業を知ろう
report 1 「数値から見たセキスイハイム」
 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー
セキスイハイムというのは、芸名みたいなものだ。
本名は「積水化学工業株式会社 住宅カンパニー」。
積水化学全体の売上げは9,262億円(2007年3月期)で、およそ半分(正確には46.4%)を住宅カンパニー(セキスイハイム)が占めている。
このページではIR情報として公表されている数字から、ハイムさんの身辺を洗い出すことにしよう。
 全国持家着工戸数・ハイム比率 全国持家着工戸数・ハイム比率

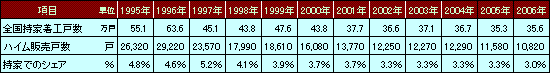

新築や改築って、1年間に日本全体で何戸くらいあるのだろう?
上の段の「全国持家着工件数」は、国土交通省が発表している数字。
国内で1年間に着工された持ち家の合計。これを多数の業者が奪い合う。
小さな工務店もあれば、大手ハウスメーカーもある。
ここ12年では1996年の約64万戸が最高値。ピークの理由は消費税UP前の駆け込み需要。
最近は約36万戸くらいに落ち着いている。
この36万戸の中の約11,000戸前後がハイムで建てられている。ハイムの仲間が年間11,000戸づつ増えていることになる。
全体のパーセンテージで3%。
33戸の新しい持ち家が建つと、1戸はセキスイハイムということになる。意外に多い。
でも10年前のハイムは、もっと頑張っていた。市場の5%を取っていた。
急いで建てたい人がユニット工法に殺到したのだろう。その後のシェア低下はローコスト・ハウスやパワー・ビルダーが
市場に進出してきたことと無関係ではない。
36万戸の市場は少子化の影響などもあり、今後は大きくならないと思われる。
その環境下で、積水化学はシェアの拡大に狙いを定めている。
また積水化学は、1981年の新耐震基準以前の木造住宅を最も有望なターゲットと考えている。
大きな地震がくれば、崩れてしまう家。このタイプの古い家が日本には1,150万戸(国土交通省推定)も残っている。
この範疇にわが家は、ピタリと合致した。積水化学から見ればターゲット通りのお得意さんだったことになる。
 ハイム・ツーユー比率 ハイム・ツーユー比率

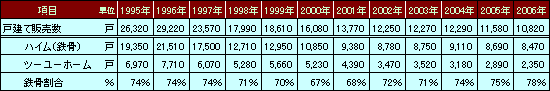

ツーユー(木造系)よりもハイム(鉄骨系)の方が多い気がするが、実際どうなのだろう?
ハイムが建てた家に占めるハイム(鉄骨系)とツーユーの件数と割合を示した。2006年度では78%が鉄骨系だ。
販売数が上下しても、比率の劇的な変化はない。ただ、2000年頃には1/3を占めていたツーユーも、
2006年には1/5に近付きつつあり下降気味だ。
わが家もハイムの主流の鉄骨住宅路線に魅力を感じた。
しかし、最近はグランツーユーの売れ行きが好調だ。その影響でツーユーの比率が上昇してるような気がするが、
実際には逆にツーユーがシェアを落としている。
グランツーユー頑張れ!
見学した豊橋の工場では、一日に10戸程度のハイム(鉄骨系)を生産していると聞いた。年間200日稼動したとして、約2,000戸。
約9,000戸の鉄骨系の年間生産数に、上記の表には載っていないハイムのアパートの4,000戸を足して13,000戸。
そう考えると全国の15%を豊橋工場で生産している計算になる。数字としてはつじつまが合っているように思う。
鉄骨系の入居者としては、パルフェ・デシオ・ドマーニ・BJの比率も気になるが、公表された数字は見当たらない。
しかし、パルフェが最も多いことは明らかであろう。
 一戸当り販売価格・平均延床面積・平均坪単価 一戸当り販売価格・平均延床面積・平均坪単価

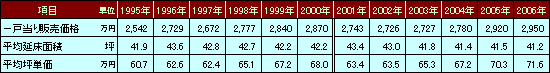

他の人はハイムの家を幾らで買ったのだろう?
お金の話はとても気になる。自分は高く買わされたのか、値引きはしっかりしてもらったのか…。
IR情報ではハイムの家が、平均いくらで売られているのかが分かる。販売価格を平均すると3,000万円をわずかながら下回っている。
これには、デシオやBJも含まれているし、ツーユーも入っているので、単純に販売価格を平均してしまうのも無理がある。
地盤改良や設備によっても金額は増減する。
ただ、おおよその金額の目安にはなる。
私の感覚では、ハイムの家はもう少し高い気がしていた。
(2001年の前の罫線が2重線になっているが、2000年以前は首都圏のみの統計で、2001年以降は全国統計)
延床面積を見ると平均で40坪より大きい。比較的広い家が多いようだ。
二世帯住宅の比率も影響していると思う。
さて、誰もが口にする坪単価だが、2001年以降の全国統計が始まって以来上昇している。
ここ数年は60万円台後半で推移してきた。しかし2005年度、ついに70万円の大台に乗った。
ハイムの家は年々高くなっている。これはハイムが値上げをしているのではなくて、購入者が高機能な住宅を
望んでいることが大きな原因だ。
ローコスト・ハウスが低価格を追求(価格訴求型)しているのに対して、
ハイムは高機能を追求(高機能訴求型)していることが数字からも分かる。
積水化学は安売路線に同調しないというスタンスが良く分かる資料だ。
安い家が目当てならば、ハイムは向いていない。
「良い家を、より安く」は積水化学の狙いではない。
「そこそこの家を、そこそこの値段で」も積水化学のスタンスではない。
「魅力的な家を、少しでも高く」が積水化学の販売戦略だ。
わが家は、三角屋根になり価格は平均よりも上昇してしまった。
高くてもハイムに魅力を感じてしまったのだと分かる。
また、付加価値の高める為に、最近の積水化学は暖房と空気(空調システム)に注目している。
 営業マン数・展示場数 営業マン数・展示場数

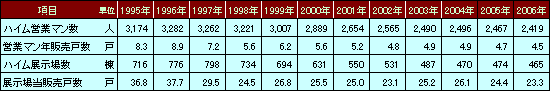

あなたが出会うハイムの営業マン。セキスイハイム全体で何人いるんだろうと思ったことはないだろうか?
なんと2,400人以上もいる。多い。多過ぎる。
また営業マンは、一年に何戸くらいの家を売っているのだろうと考えたことはないだろうか?
私はとても気になった。それによって彼らの熱の入れようが分かるからだ。
統計上では平均4〜5戸を売っている。ただ、この統計にはアパート販売の年間4,000戸は含まれていない。
アパート専門の営業マンの存在を考慮すると、一般住宅向けの営業マンの年間販売戸数は6〜7戸というところだろうか。
つまり、2ヵ月に1軒のペースで契約をしていることになる。私には予想以上に多い感じがする。
あなたと商談中も、同時進行的に数件の商談を抱えていないと、この数字の達成は不可能。しかし1996年当時には、月に1軒の
ペースで契約を取っていたと考えられる。その当時は、寝る暇もなかったことだろう。
積水化学は営業の質的転換を目標に掲げている。しかし、この目標の達成が最も難しいようだ。
2,400人全員のスキルアップは簡単ではないだろう。
積水化学と言えども予定通りにいかないこともあるのだ。
工場では機械で家を作るが、人である営業マンを作り上げるのは人だから。
ハイムの展示場数は465件。「展示場の維持費が高いから、ハウスメーカーの家は高い」との非難の声もある。
実際には、1展示場当たり年間で23戸の家が売れている。そう考えると、展示場の維持費が販売価格を押し上げているわけでも無いと感じる。
465件の展示場は妥当な件数ではないだろうか。
展示場の来展者からの受注率は高いそうだ。わが家が正にそれだ。
私は、数多くのハイム展示場を見て回った。これでは、積水化学の思う壺だ。
ハイムとの契約に向けて一直線に進んでいた自分が、今から振り返るとよく分かる。
 強点住宅受注 強点住宅受注

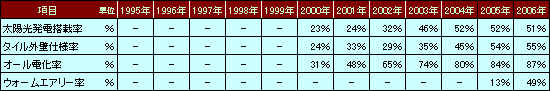

従来から太陽光発電・タイル外壁・オール電化の3項目をハイムは付加価値を上げる為の強点と呼んできた。
現在のハイムでは当たり前になったこれらの機能も、その歴史は意外に浅い。統計を開始した2000年を見るとオール電化は
1/3しか採用されていない。太陽光とタイル外壁は1/4が採用していただけだった。
それがたった5〜6年でオール電化率は84%になり、太陽光とタイル外壁も半分以上の家が採用するようになった。
1900年代のハイムの一番の魅力はユニット工法であり、それをアピールする売り方だった。
しかし、2000年以降はその路線を巧妙に変化させることに積水化学は成功した。
ユニット工法に加え、光熱費ゼロハイムというコンセプトを考え出し、強力に推進して来た。
タイル外壁に関しては、ライフサイクル・コスト(LCC)というコンセプトで購入者の心をつかんだ。大したものだ。
パナホームは積水化学のマネをしているだけだ。ただ困ったことに、
モノマネ芸人が、本人よりも人気がでてしまう場合もある。要注意。
その点、同じユニット工法であってもトヨタホームは光熱費ゼロやLCCのような価値のアピールには成功していない。
もしハイムとトヨタホームが競合した場合には、ハイムは高機能住宅をアピールすることにより、
価格はトヨタより高くても勝てる戦術で攻めてくることになる。
これはわが家が、価格的には安かったトヨタを断った事実からも証明済だ。
わが家は積水化学の狙い通りに3つの強点を全て採用している。ああ、積水化学にしてやられたのだ。
こう見てくると、わが家がハイムを選んだことは、非常に納得がいく。
積水化学、なかなかやるな。
高機能を追求する戦略が、坪単価UPに直結する。
2005年度には坪単価平均が70万円を越してしまったが、今後も更に上昇することだろう。
最近、急に強点として位置付けられたのが、ウォームエアリーだ。「あったかハイム」はセキスイハイムが最も競争力を
感じているキーワードだ。発売2年にして採用率は50%になった。他の強点と比較しても、急激な浸透率は目を引く。
また、タイルの伸びの鈍化および、太陽光の頭打ちには今後は注意が必要だ。
  |

hints
積水化学工業のHPに行って、自分の目でIR情報に目を通してほしい。
文字情報だけでなく、決算説明会などの音声配信などのコンテンツもあり興味深い。

|  |
|---|
|
|---|
|
 |

