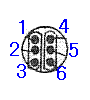|
|
|
スイッチ位置変更 プラン検討のツケ
プランのセッションで、照明・スイッチ・コンセントの検討が集中力が続かず、途中でギブアップしてしまったことを書いた。 しかし人間とは身勝手なもので、入居後に位置が気に入らなくなり、 スイッチと照明の対応関係と、コンセント位置などを有料で作業をしてもらった。 そのことを、以下に書こう。理解するのは難しいかもしれないが頑張って読んでほしい。 まず、下の図1をご覧いただきたい。これはわが家の電気図をスキャンしたもの。 図面には、照明・スイッチ・コンセントなどの位置が書き込まれている。 それぞれの記号が何を示しているかは 図面をじっくりと見ていると、何となく分かってくる。 図面は真上から見た位置や図形を示している。つまり平面的な情報が基本になっている。 一方、高さ情報は「2FL+1070」のように注釈として書かれている。「2FL+1070」は2階の床から1070mmの高さという意味だ。 でも素人には、1070mmと言われても妥当かどうかピンと来ない。 しかし、位置の妥当性は現場で確認すれば一目瞭然。電気屋さんが工事をしている途中で、クロスが張られていなければ、 位置の変更は比較的簡単だ。 監督に連絡を取り「施主の責任において、どうしても位置を変更したい」と告げよう。 現場監督のOKを取ってから、電気屋さんに依頼するのが望ましい。 ハイムのOKが無い状況で、施主が職人さんに直接頼むと、職人さんを困らせることになるので注意。 黒丸が三つとか二つ縦に並んだ記号がスイッチを示す。 そのスイッチと照明がフリーハンドの曲線で結ばれているのが分かるだろうか。 どのスイッチを押せば、どの照明が点くかが分かるように図面は作られている。 しかし、予備知識を持った人向けの図面であり、知識の無い施主には理解困難なことは確かだ。 図面の見方が分からなければ、営業やインテリアコーディネーターを捕まえて説明を聞くことだ。 待っていても向こうから親切に説明してくれることはない。
わが家では、結果的に数箇所のスイッチを変更してもらったのだが、ここではダイニング・キッチン・リビングのスイッチを 説明する。他の箇所で変更したスイッチもルールは同じだ。 図1の中心に6つボタンのスイッチが書かれている。 分かりやすくする為に、それぞれのボタンに1〜6の番号をつけよう。下の左側の図のように左側が上から1、2、3。 右側が上から4、5、6。 これを実際のスイッチに割り振ったのが、下の右側の写真だ。驚いたことに、左側の図を180度回転した位置に 同じ番号が来ている。 どうして、こういうことになるのかというと、このスイッチは図面上で逆方向の壁面に装着されるからだ。 そうすると、上下が逆転してしまう。図面上で漫画の吹き出しのように書いてある箇所にスイッチがある。 私はこの原理が分かるまで随分と時間が掛かった。多分、私の脳年齢は60歳代だろう。 南に向かって車を走らせている時に、地図をサカサマにして見るのと同じようなものだ。(返って分からないか…)
下の図2をご覧いただきたい。1、2、3のボタンに注目してみよう。 実際のスイッチでは3が一番上にくる。このボタンを押すとリビングの中央の主照明が点灯する。 その下の2番を押すと、スイッチ近くの階段横にあるダウンライトが二つ点灯する。 一番下の1番を押すと、一番離れた窓際のダウンライトが二つ点灯する。 3つの縦並びのボタンが、上から順に、中距離、近距離、遠距離の照明に対応していた。 私は、この並びが非常に気になった。私には上から順に、遠、中、近の方が分かりやすい。 そうすれば、ボタンの並びが照明の位置関係を反映するからだ。 稲垣さんに、並べ方のルールを聞いてみると、「部屋の主照明を一番上のボタンに対応させるのが普通です」との返事だった。 確かにその基準は分かりやすいかもしれないが、他のボタンで戸惑ってしまう。私は位置関係にこだわった。 ちなみに4、5、6のボタンは、私の希望とは逆の近、中、遠の順番になっていた。 入居後しばらくは、スイッチをこの配置のまま使ってみたが、私にとっては使い難かったので、 ハイムに頼んで変更してもらうことにした。もちろ有償で。 本当は工事中に変更をお願いしたのだが、電気屋さんも監督も「一旦は、図面通りに完成させてほしい」との返事だった。 図面通りのスイッチ位置で社内検査を通したかったようだ。 私は仕事で立ち会えなかったが、あのニヤニヤ顔がトレードマークの電気屋さんが作業をしてくれたとのこと。 その結果が、下の図3の図面。フリーハンドのつながりの線はそのままだが、照明の番号を変えたので見ていただきたい。 スイッチの1〜6の並びと、実際の照明の1〜6の並びを比べてほしい。 実際の照明のレイアウトが、ボタンのレイアウトと一致している。 つまり見たままの位置にあるボタンを押せば、思い通りの照明を選べるようになった。この変更を家の中にある他のスイッチにも施した。 この変更はわが家では好評だったが、本当に使いやすいかどうかは各自で判断してもらいたい。 他のHMでは、照明スイッチに名前シールを貼るタイプを使っている場合もある。そこに「主照明」とか「窓側ダウンライト」 などど書いてある。便利そうだし、これが好きな人もいる。また、ハイムでも頼めば、そういうスイッチを装着してくれるらしい。 ただ、私は個人住宅は極めてプライベートな空間なので、こういうユニバーサル・デザイン的な分かりやすさを持ち込むことに 抵抗を感じる。わが家は会社の会議室ではない。 また、ここでは書かなかったが、照明スイッチを二箇所から操作できるようにすべきだったと後悔している箇所もある。 これは、入居後の作業では対応不可能なので、プランを完璧にするしかなかった箇所だ。残念。
ウォシュレット用のコンセント位置も、入居後に気になったので、変更作業をしてもらった。 まず、下の写真1をご覧いただきたい。これは1階のトイレとウォシュレット用のコンセントだ。 ハイムではウォシュレット用の電源は、便器に向かって左側の壁から取るのが標準の仕様となっている。 わが家は1階にも2階にも「サイド手洗い器」を付けた。ただ、1階のトイレは入って右側に、2階は左側に付けた。 1階と2階で逆方向にしたのは、特に理由があってのことでなく、いつの間にかそうなっていたように思う。 もう一度、1階のトイレを整理すると、入って右側に「サイド手洗い器」があり、何も無い左の壁面からウォシュレット用の電源を取っている。 さて、次に写真2をご覧いただきたい。2階のトイレだ。入って左側に「サイド手洗い器」があり、またウォシュレット用の電源も左壁から取っている。 すると、コンセントの位置が「サイド手洗い器」の棚の中に来てしまう。ここからウォシュレット用の電源を取ると、棚が使えない状態になってしまう。 実は、こんな状態になることに関しては、ハイムからの事前説明は無かった。もし知っていたら、1階と同じように右壁に「サイド手洗い器」を 持ってきたはずだった。 さて、上のスイッチ位置の変更作業の時に、ウォシュレット用のコンセントを右壁に移動する作業を一緒にしてもらうことにした。 しかし、ウォシュレット用の電源コードは左側から出ているので、これを右に回すには、便器の後ろの細い隙間を無理して通さなければ ならない、またコードが短ければ延長コードを使う必要もあった。 ニヤニヤ顔の電気屋さんに、右壁にコンセントを付けてもらう相談をしたところ、電気屋さんから素晴らしいアイディアが 出たらしい。 写真3にあるように、背面の壁から直接電源を取ってしまう方法だ。 これは写真1よりも、コンセントが隠れているため、最適な方法だと思える。 こんな良い方法があるなら、初めからこれでやってくれればいいのにと思った。 写真1よりも写真3の方が好みの方は、この写真をハイム見せて「このようにコンセントを付けてほしい」とリクエストをしたらどうだろう。 このページで紹介した、照明スイッチのボタン変更及びトイレのコンセント変更の料金は合計で18,900円だった。 これくらいの金額なら、プランで完璧を求めなくても、後で料金を払って作業をしてもうのも手かもしれない。
上の記事の写真3の工事を、わが家は特別にしてもらった。 あの時点では最善の方法だと感じ私は満足した。少なくともハイム標準の電源の取り方よりも優れているように見えた。 しかし、上には上がいるものだ。 このHPの掲示板で御馴染みのPochioさんが、わが家の方法を更に進めて、コンセント及びアースを背面の壁の向こう側に収めてしまった。 温水用の水道線を便器の背後に直結し、化粧カバーに開いている小さなホールに電源とアースを通している。背面のカバーは特別な加工もせずに綺麗に収まっている。 この写真を見たら、誰もが同じようにして欲しいとハイムに頼むかもしれない。でも、Pochioさんは個別対応としてハイムに作業をしてもらっていることを了承していただきたい。同じように工事してくれる保証はない。 でも、これからハイムで家を作られる方は、この写真を印刷してハイムに見せて相談するのも賢い方法かもしれない。そのようにこの写真を使うことに関してはPochioさんの了承をいただいている。 ありがとう。Pochioさん、とてもスッキリしていますね。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意:検索エンジン等でこのページに直接来られた方は、ここをクリックしてTOPページに移動して下さい。 |