 |
 |
 |

その他の変更点
あれやこれや
 廊下のダウンライト 廊下のダウンライト
下の図を見ていただきたい。灰色の部分が廊下で、丸い黄色が2つのダウンライト。
ダウンライトの位置は廊下の中心を通らずに片寄っている。片側が35センチで、残りが48センチ。
普通なら真中に配置したいはず。
梁が天井の中心を通っているので、ここにはダウンライトが付けられないらしい。だから片寄ってしまう。
プラン検討の時にも、四者立会の時にもそのような説明を受けた気がする。
「そんなものかな」と思うぐらいで、その時は気にしなかった。
さて、据付が終わると、既に取り付け位置の天井から電源コードが垂れ下がっている。
「これは、かなりずれているなぁ」と感じた。何だか気分が悪い。直したいと思う。
ハイム側に確認すると、センターに移動するのは無理との返事。やはり梁が走っていることが理由。
そういえば、ハイムで建築された方のHPで同じような記事を読んだことがあった。
その方は、中途半端にセンターを外すのであれば、思い切って端に寄せたかったのだが、
気付いたのは工事終了後で手遅れだったと書いていた。
 | 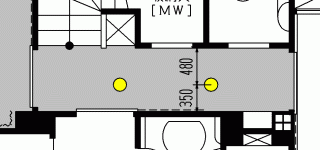 |
 ダウンライトは、2:3の割合の
ダウンライトは、2:3の割合の
 位置に付けられる予定だった。 位置に付けられる予定だった。
 2つのダウンライトの間隔は 2つのダウンライトの間隔は
 120センチ。 120センチ。
|  |
ある日、電気屋さんや大工さんとこの話になった。
「このダウンライトって、センターに配置できないんだよね?」とハイムから聞いた事を確認する。
「いいえ、できますよ」と電気屋さん。
「うっそー。ハイムが駄目だって言ってたよ。梁があるから駄目だって」と半信半疑の私。
「大丈夫。何とでもなります。もし無理でも、何とかしちゃいますから」と彼ら。
偶然現場に居合わせた西山さんも驚いた顔で「無理なんじゃないんですか?」と彼らと問答をしていた。
何だかよく分からないので、監督と職人さんの間で電話で話をしてもらうことにした。
しばらくして監督から電話があった。「2つのダウンライトの間隔は少し変わりますが、廊下の真中には配置できそうです」
との返事だった。
やがて変更の作業が終わり、ダウンライトは廊下の真中に付いた。これなら不満なし。
もし、私が職人さんに一言確認しなかったのなら、図面通りに片寄った位置にダウンライトは付いたはずだ。
ハイム側からの説明を信用しないということではないが、ダメモトで職人さんに質問や依頼をすることは意味がある
場合がある。
既に入居して、ダウンライトの位置に不満を感じている方には、知らなかった方が良い記事になってしまったかもしれない。
 |
 |
 |
|---|
 大きな穴の左の小さな穴が初めの位置 大きな穴の左の小さな穴が初めの位置 |
 |
 現在の状況。きれいに中心にある。 現在の状況。きれいに中心にある。 |
 階段の壁への穴開け 階段の壁への穴開け
「台所スイッチの問題」のページでわが家の2階には壁が少ないことを書いた。
リビング階段があるが、
1メートルの高さの腰壁で3方向を囲まれたところに、階段がぽかっと開いている感じ。なんだか不思議。階段はコの字形をしている。
プラン検討中に壁を増やしたくなって、階段の腰壁の1面をあえて天井まで立ち上げることにした。下の図の青色で塗られた部分。
広いリビングダイニングの視界を遮ることになるが、部屋に変化が出て面白いはずだ。
厚さは7センチで、幅は145センチの1枚の板。
この壁は存在感が強いかもしれないし、あまり気にならないかもしれない。頭の中で想像してみるが、なかなかイメージが掴めない。
特に階段途中から見上げた時の印象が気になるのだが、全く分からない。現場で確認することが待ち遠しかった壁。
 | 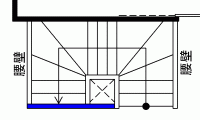 |
 リビング階段
リビング階段
 冷暖房はリビング階段によって 冷暖房はリビング階段によって
 1階にまで流れてしまう。 1階にまで流れてしまう。
 効率が悪い。 効率が悪い。
|  |
腰壁の高さの3面と、階段は工場で作られてきたが、天井までの立ち上がりは2階の大工さんの仕事。
出来上がってくると、頭の中のイメージと実物とは、やはり違っていた。
横から見ると薄い板なので気にならないが、正面から見ると少し閉塞感がある。
そこで、壁の上の部分に穴を開ける
ことにした。今回も自分で図面を書いた。図面としては単純。16センチ×40センチの縦長穴を3つ均等に配置した。
ハイムに図面をメールで送るのと同時に、2階の大工さんにも図面を手渡す。大工さんに私の意図を直接説明できるので
勘違いはない。間もなく満足のいく細工が出来上がった。
私は図面を書く技術があるわけではない。見よう見まねだ。でも施主が図面を書くことは珍しいと思う。
のんびりしていると大工仕事が終わってしまうので、慌てて図面を書いた。
では図面を書かない多くの方の場合はどうしたらいいのだろう。現場を見て、どうしても変更しい箇所が出てきた。
でも大工仕事は日々進んでいくような場合だ。
簡単な内容であれば、大工さんとの口頭確認で作業をしてもらう。その場合はセンスの良し悪しは大工さんによって大きく左右される。
急いで設計やインテリアコーディネーターに相談する方法もある。ただ、彼らが現場に来れるスケジュールが合わないと、ちょっと困ることになる。
どうすればいいのかを現場監督に相談することが良いと思う。
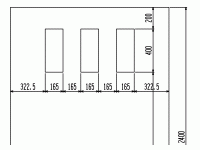 |
 |
 |
 Davidが書いた壁の穴の図面 Davidが書いた壁の穴の図面 |
 |
 階段から見上げる。きれいに開いた穴。 階段から見上げる。きれいに開いた穴。 |
 通称は暖炉 通称は暖炉
人造大理石のカウンターの柱。また各種スイッチが縦に並んだ柱。ここに通称暖炉がある。何となく暖炉みたいな形なので家族で、そう呼んでいる。
下の図の緑色の部分。ここは二階のキッチンで使った水を1階に降ろす配管用に必要だった。物理的に必要なのは20センチほどの高さだが、
85センチの高さにインテリア手配の天板を置いて、ちょっとした台として使うことにした。
 | 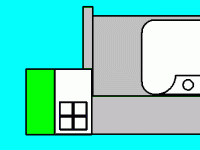 |
 緑色の部分が今回のテーマ。 緑色の部分が今回のテーマ。
 天板はインテリア手配。 天板はインテリア手配。
 幅60センチ 幅60センチ
 奥行30センチ 奥行30センチ
 高さ85センチ 高さ85センチ
|  |
この中は空洞なので、くり抜いたり、扉をつけて収納用に使えるようにするのか、それとも単なる天板のあるテーブルにするのかは
プラン段階では決めれなかった。ここも実物を見ないとイメージがつかめなかったから。
実際に見てみると、空洞をふさぐのは惜しい。やはりくり抜くことにした。中はクロス仕上げで、底の板や扉は付けない。
なるべく安くしたかったのが理由。底は入居後に現場で余った床材を自分で張った。
さて、また自分で図面を作った。今回もハイムに図面をメールで送るのと同時に、2階の大工さんにも説明しながら手渡す。
やはり大工さんに直接説明できれば勘違いはない。ここも満足のいく仕上げだった。
さて、これらの作業の金額だが、予想より安かった。それぞれ数千円という金額だったと記憶している。
金額が分かったのは大工仕事が終わった後だった。ビックリするほどの高い金額だったらどうしようと心配だったが、この程度の
金額だったら、他の箇所への造作も考えたかったと、ちょっと後悔している。
自分で図面を書いたから安かったのかどうかは分からない。
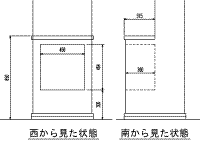 |
 |
 |
 またまたDavidが書いた図面。 またまたDavidが書いた図面。 |
 |
 暖炉と言われれば、そのようにも見える。 暖炉と言われれば、そのようにも見える。 |
 あれこれ あれこれ
これ以外にもあれこれと現場で変更をお願いした。
その時点では、それなりに検討できたと思っていたのだが、決して十分に見ていなかったことが入居後になって分かる。
これからセキスイハイムで家を建てるなら、プラン検討段階でも現場でも、しっかりと見ることをお勧めする。
|
 |
